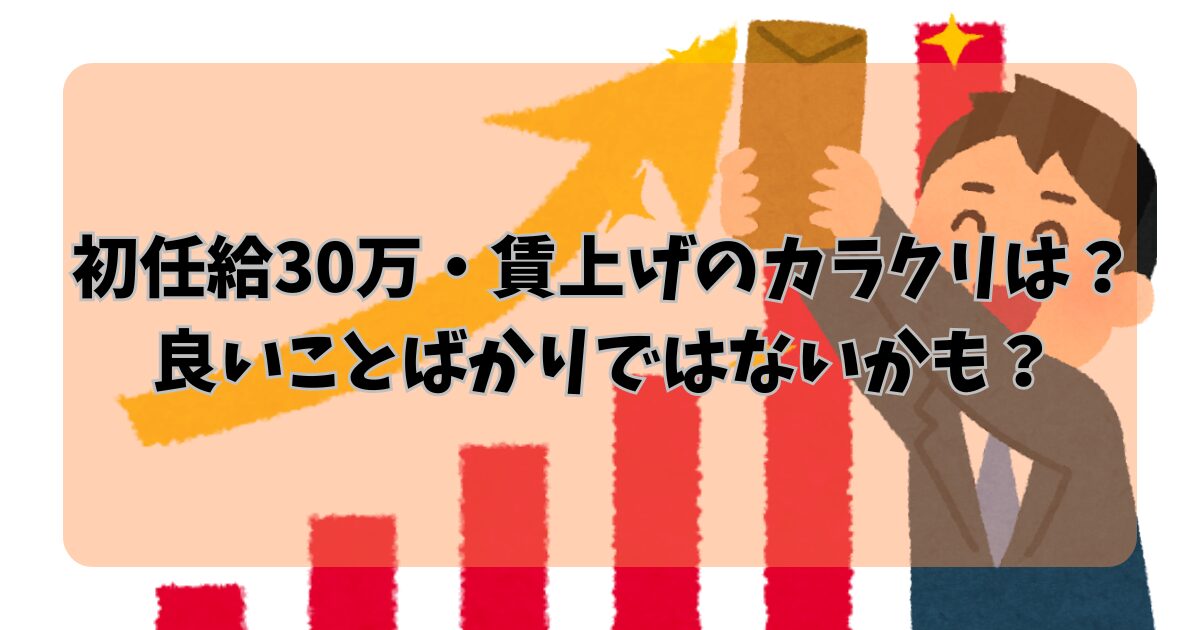こんにちは。じんまいです。
さて、春といえばお花見…ではなく春闘ですね!
今年も結果が出ましたが、2年連続で平均賃上げ率5%以上という、労働者にとって嬉しい結果となりました。
うちは上がらないから春闘なんて関係ない…という方も、世論として労働者への還元という考えが強まれば、いずれ恩恵を受けることになります。
世の中が初任給UPや賃上げに湧いている訳ですが、私は良いことばかりではないと考えています。

給料上がるの嬉しくねーの?

もちろん嬉しいです!が!
そう、賃上げには原資が必要です。
もちろん儲かっていて、労働者の利益分配率を引き上げているだけなら問題ないのですが…
蓋を開けてみたら、従業員にとってマイナスだった…という状況を招いてしまう可能性があるのです。
初任給の引き上げについてはこちらの記事もどうぞ!
なぜ賃上げの風潮なのか
賃上げは人件費が高騰するということで、経営にとってはコストの増加を意味します。
当然、会社としては喜んで賃上げをすることはありません。
優秀な人材の確保や、従業員のモチベーションアップを計り、業績を拡大するための投資(コスト)としておこないます。
しかも、一度基本給をあげると会社都合で一方的に下げることは難しいため、リスクが高く慎重にならざるを得ません。
それでも近年は賃上げの波が続いています。
なぜなら、少子高齢化により働き手が不足しており、労働者の価値が上がっているからです。
各社で奪い合っていると言っても良いでしょう。
例えば、以下のような条件だとどうでしょう?
A社が初任給23万円で募集
B社が初任給30万円で募集
同業で他の条件は同じ
もちろん、お金が全てではないので全員がB社に入る!ということはないでしょう。
ただし、求人を見た時に先に目に入り、魅力的に映りやすいのは給料の高いB社でしょう。
このように、賃金を上げなければ人が集まらず経営が立ち行かなくなってしまうのです。
これは悪い賃上げと言えるでしょう。
業績が良くて利益が出ているから賃上げをするのが正しい順序ですが、仕方なく賃上げせざるをえない状況になっているのです。
コレではコストプッシュ型インフレを引き起こしてしまうでしょう。
賃上げのデメリット
前述の通り、利益が出ている上での配分であれば問題ありません。大変喜ばしいことです。
ですが、利益の追いついていない賃上げではどこかに必ず皺寄せがいきます。
- 手当でかさまし
- ボーナスの減少
- 福利厚生の廃止
- 昇給額が少ない
- 仕事の要求値が上がる
- 雇用が減る
このように、何処かを減らしたり、誤魔化しながら初任給やベアの原資にしている可能性があります。

これじゃ喜べねーじゃねーか…

基本給は簡単には下げられませんが、業績悪化でボーナスカットや手当の廃止は可能です。
大抵の求人は手当も込みの額を初任給として記載しています。
この手当でかさましされた状態だと、思ったよりボーナスが貰えずガッカリするでしょう。
何故なら、ボーナス⚪︎ヶ月分というのは基本給にかかるからです。
例えば同じ初任給30万でも
A:基本給30万
B:基本給15万+手当15万
だとB社はA社の半分しかボーナスが貰えないことになってしまいます。

これを悪用して、基本給を下げて、ボーナスのヶ月数を増やすという荒ワザがあります。

この例だと、A社の3ヶ月分は、B社にとっては6ヶ月分…B社が魅力的に映っちまうじゃねーか!
福利厚生については、求人票を確認するのはもちろんですが、細かい内容については社員口コミサイトなどを確認して、生の情報を手に入れましょう。
特に、家賃補助や退職金、企業年金などは額も大きく、人生設計に大きく影響するため必ず確認が必要です。

ウチは社員寮がある代わりに家賃補助は無し!

退職金も定年までいっても400万ないくらいかな…
また、初任給が高い代わりに、毎年の昇給額を抑えている企業もあります。
これについては一概に悪いとは言えません。
長く働く年功序列、終身雇用を念頭に置いていなければ昇給の先取りと考えられるので全く問題ありません。
事前に納得していたり、転職を前提に働いていないと思ったよりもモチベーションの下落に直結します。
私のところも、定期昇給が一律1500円+能力給が0〜500円とかいうとても残念な制度になっていますが、どこか真面目に働くのはアホらしいな。という気持ちが否めません。

お前んとこ初任給高くないんだからちょっと違くね…?

…シンプルに残念企業ですね
一貫してお話ししている通り、賃上げには原資が必要です。
今までの方法のように別の場所をコストカットをして捻出していっても、いつか限界が来てしまいます。
そう言った時に何が起こるかと言えば不採算人員の整理、俗にいうリストラです。
コストが高いのに成果が出せていない社員は機械に代替され、優秀な社員の給料アップの原資にされてしまう未来が近いうちに来てしまうかもしれませんね。
従業員はどうするべきか
我々従業員はどうするべきなのか。
新卒就活など、求人を探している段階であれば業績や財務状況をチェックすることで、賃上げをする原資や体力があるのかが多少わかります。
- 純利益が安定しているか
- 社員一人当たりの利益が増加しているか
- 自己資本比率があまりにも低すぎないか
などを確認することで大ハズレ企業を避けることができます。
投資家のことを考えている企業であれば、IRの中に、業績推移をグラフを用いて説明しているページがありますので、小難しい資料から探す必要もありません。
社員数については、有価証券報告書や会社概要のページに従業員数が書かれていることが多いので探してみてください。
すでに就職しているのであれば、会社の業績UPに貢献できるよう働く必要があるでしょう。
仕事熱心になり学び続けることを辞めなければ、生産性が上がることで良いカタチでの給料アップが望めます。
万が一、会社の経営が立ち行かなくなり人員整理があったとしても、生産性の高い社員は切られません。
最悪の事態として、会社が倒産したとしましょう。この場合でも、スキルを持ち生産性の高い社員はどうとでもなります。
他社だって生産性の高い人材が必要です。自ずと再就職しやすいでしょう。
逆に、ぶら下がりを続けてきた社員(キャリアを意識してこなかった社員)は早い段階で切られますし、いい条件での再就職も難しいでしょう。
自身のことを考えると、仕事には全力で取り組み、それなりにスキルアップをしておくことが最強の保険になるのです。
まとめ
初任給30万や賃上げのカラクリのお話でした。
無理のある賃上げはどこかで必ず、皺寄せがきます。
利益が追いついていないということは、別のコストを削って付け替えているにすぎないのです。
今回は社内のことにだけ目を向けてみましたがマクロで見ると、コストプッシュ型インフレが起こり、物価上昇で生活が辛くなったりもするでしょう。
このように急激な賃上げの流れはいいことばかりではなく、副作用を生じることがあるのです。
我々労働者にとって、とにかく働き、スキルを身につけキャリアを形成していくのが変化の激しい社会で生き残る術と言えるでしょう。

私自身、できているかは怪しいですが…

業界資格を取るとか、そんな些細なことからでいいと思うぞ!
最後までお読みいただきありがとうございました。