ブログを初めて1周年。ダメもとで申請していたGoogleアドセンスの結果が届きました。
13回目のチャレンジ。なんと合格の通知が来ました。
諦めかけていましたし、1年経つ寸前でモチベーションも下がっておりブログはお休みしようと思っていました。
同じように、Googleアドセンスの合格に向けて頑張っている方へ、少しでも参考になればと思い、今まで取り組んでいたことと、直前にやったことを記憶を頼りにつづっていきます。
- 2025年のアドセンス合格談を知りたい方
- 何度もアドセンス審査落ちしていて心が折れそうな方
- YMYLジャンルのブログで合格を諦めそうになっている方
結論
- 特化ブログに寄せていく(メイン8:雑記2)
- 雑記部分の露出を減らす
- E-E-A-Tを意識する

まさか合格すると思っていなかったので本当に驚いています
今までの申請記録
まずは今までの申請記録とアドセンス対策で行っていたことをまとめてみました。
今までのアドセンス落選記録
1回目:2024/11/11
→プロフィール・お問い合わせフォーム・プライバシーポリシーを作成
記事は数記事だけでダメ元で申請。
2回目:11/26
→数記事追加・ヘッダーメニューを追加・画像をリサイズするプラグインを導入
3回目:12/10
→数記事追加・過去記事をリライト(長文の解消や視覚効果を追加)
記事タイトルにSEOを意識し始める。一般記事扱いだったプロフィールを固定ページに移動。
4回目:2025/1/5
→ドメインパワーを意識して『ブログ村』に登録
トップページのオススメ記事スライダーを追加
ヘッダーメニューに表示するカテゴリを厳選
固定ページにカテゴリやタグ一覧を表示する形に変更(当時はカテゴリ数やタグ数がとても多かったです。)
5回目:1/19
→記事内のリンク切れを修復
数記事追加
6回目:2/5(この時点で投稿記事数は32記事)
→個別銘柄の解説をしていた記事を非公開に移動
アドセンス用の審査コードの改行を削除
7回目:3/1
→カテゴリの見直し
プライバシーポリシー内にあった免責事項を単独化
フッター・ヘッダーメニューの整理
8回目:3/31
→楽天お買い物マラソンでオススメしていた市販薬「ロキソニン」の記載を削除
9回目:5/22
→Googleコンソールのサイトマップを再度登録しなおし
10回目:6/11
→記事追加
11回目:7/18
→記事追加
12回目:8/19
→記事追加
13回目:10/20→10/29合格通知
→chatGPTに相談をするようになる
取り組んだことは後述
- 運営歴1年弱
- 不合格理由は「有用性の低いコンテンツ」
- 3日に1回、月に10回の更新を目標に投稿
- 公開記事数は123記事
- アフィリエイト/楽天/Amazon広告あり
- アクセス数は1日に50件あれば多い方
- 流入経路のほとんどはブログ村
- Google検索からの流入は週に20回前後
合格直前に取り組んでいたこと
アドセンス合格に向けて約1年。様々なことに取り組んでおり、実際に何が有効だったのかは明確には分かりません。
そのため、合格の直前で取り組んでいたことをご紹介していきます。
- chatGPTに相談
- FIRE関係の記事を作成し特化ブログ寄りに変化
- 基幹記事を作成して内部リンクを充実
- カテゴリの刷新とnoindex
- トップページの刷新
- YMYLジャンルの記事に外部リンクを追加
プラスして、更新頻度を2日に1記事を目標に変更していました。
chatGPTに相談
まずは、chatGPTに当ブログのURLを張り付けて、ブログのコンセプトとアドセンスに合格できないことを伝えました。

辛口でいいので評価をお願い!と伝えたら…
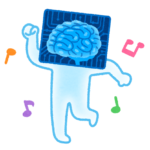
FIREブログの皮をかぶった雑記ブログ!何のサイトなのか伝わってない!
と、ストレートに表現。薄々思っていましたが、ここまで明確に言われると直視せざるを得ません。
そして、改善案をずらーッと3000文字を超えるボリュームで提示してくれました。
とにかく、
- 専門サイトとして作り上げること
- YMYLジャンルを取り扱うなら信頼性を高めること
- ユーザーが回遊しやすい作りにすること
- 結論を早く知れるようにすること
を進められました。

約2カ月をかけて、chatGPTの言うことを素直に聞いて進めていきました。
FIRE関係の記事を増やした
まずは、ブログのテーマである『FIRE』についての記事を増やすことにしました。
というのも、直近で投稿していた記事は適応障害やコントローラーの修理、ミニマリスト関係ばかりであり、直接的にはFIREに関係の無いものばかりでした。
chatGPTの指摘通り、雑記ブログになっていました。
というのも、FIRE関係の記事は多くの先人が解説しており、作っても無駄だろうという考えになってしまい尻込みし、ネタ切れになってしまっていました。

自分が今更書いても他サイトの方が詳しくて分かりやすいし、自分レベルの人が書いてもしょうがないか…
ですが、chatGPTの提案にある『基幹記事』の作成を考えると、そういった既にほかの人が発信している内容にも触れていく必要がありました。
たとえば、FIREの種類の解説などです。
既にありふれている情報を改めて自身の言葉で記事を作成しました。
当然、他サイトの焼き増しになってしまっては意味がありません。
大切なのは、自身の経験やブログのテーマに合わせた内容にブラッシュアップすることだと感じています。

自身の属性でもある『高卒や低年収でも再現性のある方法』というのをテーマに書くことを意識しました。
基幹記事を作成する
ユーザーの利便性を上げる為に、内部リンクを充実させていくのは今までも取り組んでいました。
ですがchatGPTに言われたのは、
やみくもに内部リンクを繋げるのではなく、『FIRE』という枠組みの中で繋げていき、『基幹』となる記事を作成して回遊しやすいようにする。
ということでした。以下が『基幹』として作成した記事です。
これを期に、ブログのコンセプトも明確化しました。ゴールに向かって取り組むべきことを一気に見れるように、ブログ自体の目次をイメージして作りました。
今までの内部リンクは、FIRE関係の記事から雑記記事に飛ばしてしまったり、テーマが乱雑になってしまっていたため、何のブログなのか分からない状態でした。
そこで、自身の考える『FIREロードマップ』を作成し、個別記事で肉付けする形に整えることで、雑記ブログから『特化ブログ』に進めていきました。
カテゴリの再編とnoindex
雑記ブログになってしまっている。という指摘を受け、カテゴリの再編成を行うことにしました。
というのも、自分自身でも

この記事はカテゴリどうするか…
と悩むことが多かったのです。
そして、グーグルアドセンスの対策を調べていると、カテゴリの乱立はNGということも多くのサイトで紹介されています。
これも雑記ブログ化せずに、特化ブログに寄せることでGoogleに何のサイトなのかを判別しやすいようにする狙いがあります。
FIREを目指す際に必要なこと以外はすべて雑記に変更し、カテゴリの数を7つから5つに絞りました。
そして、新たなカテゴリに適さない記事で、雑記に入れるほどでもない記事については非公開に変更しました。
具体的には日記に近い記事です。
特化ブログにする上で雑記率は2割以下に抑えるべき。というアドバイスをchatGPTに伝えられていたためです。
加えて特化ブログ感を出すために、カテゴリページやタグページにnoindexの設定を施して、サーチコンソールのサイトマップを登録しなおしました。
トップページの刷新
当ブログではWordpressテーマの『cocoon』を使用しています。
トップページについて、ほぼ初期設定のままだったのを刷新しました。
chatGPTから言われていた以下のことを解消するために取り組みました。
- 人気記事ランキングに雑記が露出
- オススメ記事に雑記が露出
特化ブログ化するためには雑記記事が表に出ないことが大切とのことなので、それぞれ雑記カテゴリを非表示に設定しました。
よくある新着記事が上から並んでいる物ではなく、カテゴリごとに表示される設定にも変更し、『基幹』へのリンクも作成しました。
少しでも特化サイトに見える構造になるように意識をしました。
YMYLジャンルの信頼性の確保
FIREブログということで、投資や資産形成をはじめ、マネーリテラシーに係る部分が多くYMYLジャンルを多く取り扱っていました。
YMYLでは、E-E-A-Tが特に大切だと言われています。
E-E-A-Tとは「Experience(経験)/Expertise(専門性)/Authoritativeness(権威性)/Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった言葉です。
chatGPTからは、信頼性を確保するため外部リンクをオススメされたため、細かい解説であっても公的機関のページにリンクするよう意識しました。
まとめ
結論
- 特化ブログに寄せていく(メイン8:雑記2)
- 雑記部分の露出を減らす
- E-E-A-Tを意識する
- 運営歴1年弱
- 不合格理由は「有用性の低いコンテンツ」
- 3日に1回、月に10回の更新を目標に投稿
- 公開記事数は123記事
- アフィリエイト/楽天/Amazon広告あり
- アクセス数は1日に50件あれば多い方
- 流入経路のほとんどはブログ村
- Google検索からの流入は週に20回前後
ココロが折れかかっていたGoogleアドセンス審査。
実際のところ何が合格の決め手だったのかは分かりませんが、忘れたころに合格することができました。諦めずに続けることが大切なんだなと良い経験になりました。
どうしても行き詰ってしまっている方は、chatGPTをはじめとした生成AIに相談をしてみると、解決の糸口が掴めるかもしれませんよ!
一人で答えのない取り組みをするよりも、相談相手がいた方が長く続けやすいのでおススメです。
最後までお読みいただきありがとうございました。






