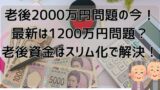社会人になったからには保険には入らないと。
そう言われたことはありませんか?
民間保険の営業マンや会社の上司、先輩、もっと身近だと両親。
周りの人が当り前のように加入している民間の生命・医療保険。
みんな入っているから。と流されて加入していませんか?
その民間保険。もしかしたら今はまだ要らないかもしれません。
- FIREを目指す場合、生命医療保険はどうすべきか
- 公的保険のカバー範囲
- 民間保険への加入を考えるべき人
- 保険見直しの節約効果
結論!
民間保険には入らず、自前保険金を作るのも一つの手!
リスクヘッジは公的保険で十分なケースも多い
リスク許容度が低い場合のみ要検討
原則不要/見直し予知あり
- 独身/扶養なし
- 生活防衛資金あり
- 会社員
- 団信加入済み
加入検討/慎重にリスク管理
- 小さな子供あり
- 先進医療を希望
- 自営業/フリーランス
- 団信なしローン持ち
生命保険や医療保険は必要なのか?
結論を述べると、生命保険や医療保険は万人受けするものではなく、条件に当てはまる人のみが加入すれば十分と考えています。
生命保険や医療保険への加入を考えるべき条件
- 生活費の半年~1年分の資産を持っていない
- 自身が亡くなったら生活が困窮する人がいる
- 日本国内に住んでいない
- お金を貯める習慣が無い
この4つに当てはまっていなければ、生命保険や医療保険は原則不要と考えています。
その理由は、日本は公的保険が充実しているから。
皆保険制度と言い、日本国民全員が既に保険に加入している、むしろ義務になっているのです。
加入している主な公的保険
会社員
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 労災保険
- 介護保険
自営業/フリーランス
- 国民健康保険
- 国民年金保険
- 介護保険
会社員であれば毎月、健康保険料が給料から天引きされているはずです。厚生年金保険料も天引きされているでしょう。
健康保険に加入していない人(個人事業主など)でも、国民健康保険料を支払っているはずです。国民年金保険料も収めていますよね?
日本人はこれでもかというくらいに、既に保険に加入しており国から守られているのです。
とても安くない額が徴収されていますが、保険の内容を理解しているでしょうか?
折角加入している保険なのに、制度を理解せずに活用できなかったり安心感が得られなければムダ払いになってしまいます。
健康保険や年金保険の補償内容を理解すれば、生命保険をはじめとした民間保険が必要かどうか、判断できるようにもなれるのです。
公的保険でどの程度カバーできているかを見ていきましょう
生命保険の範囲(国民年金・厚生年金)
生命保険の大前提として自身が亡くなった時に、金銭的に困る家族が居ないのであれば原則不要です。
そして、小さな子供や働けない配偶者がいる場合でも国民年金や厚生年金の制度である、遺族年金である程度はカバーできています。
例えば、国民年金の『遺族基礎年金』という制度では、被保険者や老齢基礎年金の受給者、受給資格のある者等が亡くなった時に、
子のいる配偶者か子(原則18歳まで)に対して、年間で1,071,000円(月額89,250円)が支給されます。(基本支給831,700円 + 子1人につき239,300円 ※3人以降は減額)
参考:遺族基礎年金(日本年金機構)
更に、厚生年金にも『遺族厚生年金』という制度があります。
こちらも同様に厚生年金の被保険者や老齢厚生年金の受給者、受給資格のある者などが亡くなった時に、生計を維持されていた遺族に支給されます。
遺族厚生年金の受給対象者は幅広く、子のある配偶者や子だけでなく、子のない配偶者や他親族も対象で、優先順位が高い者に支給されます。
遺族厚生年金の支給額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4の額になります。

報酬比例部分ってことは、若者世代だと加入期間が短いから保険としては弱いんじゃないのか?

いい質問ですね!おっしゃる通り報酬比例部分は現役時の収入と加入期間で決まります。ですが、遺族厚生年金には最低保証となる特例があるのです!
子のある配偶者・子・子のない配偶者への支給で、報酬比例部分が300月に満たない場合は300月とみなす特例があります。
この場合、年収400万円であれば年間410,664円(月額34,222円)の支給が得られます。
平均標準月額報酬(400万/12=33.3万)×5.481/1000(決められた計算式)×加入月数(300月)=報酬比例部分
※報酬比例部分に3/4するのを忘れずに!
『遺族基礎年金』と『遺族厚生年金』は併給が可能なので、
年間1,481,664円(月額123,472円)の支給になります。
しかも、遺族年金は非課税所得のため税金は引かれません。
もちろん、子供有でこの金額では生活できません。
足りないと思う分を生命保険でカバーするのが大切なのです。
個人的には、子供+働くことができない配偶者。くらいの条件でなければ生命保険の加入は不要と考えています。
以下は年収400万円の会社員が無くなり、残された配偶者が年収300万円で働き始めた場合のモデルケースです。
夫(故人):年収400万円 厚生年金加入年数120カ月(300カ月とみなす)
妻:年収300万円
子:1人(18歳以下)
【収入】
妻:年収300万円*0.75(控除概算)=手取り年収225万円(月額187,000円)
遺族基礎年金:年間1,071,000円(月額89,250円)
遺族厚生年金:年間410,664円(月額34,222円)
合計:年間手取り3,731,664円(月額310,972円)
※遺族年金には前年の所得が850万円までという所得制限があります。
これだけでも十分生活が成り立つと思いませんか?
更に、残せるのは年金だけではありません。資産だって残せます。
FIREを目指している以上、それなりの金額が残っているでしょうし、団信でローンを組んでいれば住宅ローンだって無くなります。
自身がいなくなったら遺族が困る。と漠然に思ってしまいますが、生命保険までかけてしまうととても裕福な生活になるかもしれませんよ。
遺族年金の支給を加味した上で、生命保険の額は決めるべし。
配偶者が働ける状態であれば、思ったよりも金額は要らないかも。
医療保険の範囲(健康保険・国保)
会社員であれば健康保険、そのほかの方は国民健康保険に加入しています。
誰もが知る補償内容として、
保険適用の医療を受けた際には自己負担が3割になる。
というものがあります。
これを『療養の給付』と言います。
診察だけではなく、処方箋での薬代など保険適用が認められている支払いについては自己負担額が以下のようになります。
| 年齢 | 負担割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 75歳以上 | 原則1割負担 | 所得が一定以上だと2割負担 所得が現役並みだと3割負担 |
| 70歳~74歳 | 原則2割負担 | 所得が現役並みだと3割負担 |
| 70歳未満 | 3割負担 | – |
| 6歳未満 | 2割負担 | – |
日本では、保険適用内であれば、良質な医療を安価で受けることができるということです。
もう一つ、代表的な制度に『高額療養費制度』というものがあります。
高額療養費制度では、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月の上限額を超えた場合に、その超えた部分について支給される制度です。
上限額は以下のようになっています。
| 適応区分 | ひと月の上限額(円) |
|---|---|
| 年収約1,160万円以上 | 252,600+(医療費-842,000)×1% |
| 年収約770~約1,160万円 | 167,400+(医療費-558,000)×1% |
| 年収約370~約770万円 | 80,100+(医療費-267,000)×1% |
| 年収約370万円未満 | 57,600 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400 |
日本の勤労者が多く属しているであろう、年収約370万~約770万円の区分であれば、月当たりの上限は8万円前後に落ち着くということです。
①計算式に自己負担額を当てはめる
80,100+(1,000,000-267,000)×1%
②()内の計算をして、基本額に加算する
80,100+7,330=87,430円が上限額
差額の約93万円は申請をすれば給付が受けられます。

自己負担100万円を一旦払うなんて、保険でも掛けてなくちゃできないぜ!

…という方にも安心の制度が整っています!
高額な支払になることが分かっている場合は『限度額適用認定証』というものを事前に取得するか、『マイナ保険証』を利用すれば窓口での支払いを限度額までにすることが可能なのです。
これらを加味すると、病気やケガをしたとしても保険適用内の治療であれば数百万といった大きな金額はかからないことが分かります。
個人的には、民間の医療保険に入る必要がないくらい、公的保険が充実していると感じています。
ただし、生活防衛資金や高額療養費制度の限度額数か月分の貯蓄も作れていない、新卒の状態であれば、資金が作れるまでは加入しておくのは一つの手と言えるでしょう。
生活防衛資金がない状態や、
保険適用外や差額ベッド代などを考えるのであれば、民間の保険が有効になりえます。
ただし、一度の入院での自己負担の総額は約20万円と言われています。
出典:入院費用(自己負担額はどれくらい?(生命保険文化センター)
この数字は高額療養費制度を利用した後に、食事代や差額ベッド代などの保険適用外の費用も含むものです。
どちらにせよ、医療保険で備えるのではなく資産形成で備えられる範囲と考えられます。
更に、健康保険に加入している会社員の場合は、『傷病手当金』という業務外のケガや病気で働けない時の給付金(最長1年6か月/標準報酬の約2/3)があります。
参考:傷病手当金(全国健康保険協会)
生活防衛資金も半年~1年程度の生活費分くらいあれば十分に立て直しできる可能性が高いでしょう。
公的保険について、もっと詳しく学びたい場合↓

FP3級の勉強をするのが最強!資格を取らなくても勉強する価値大アリ!
お金に困らない人生を送ることができるようになりますよ!
生命医療保険への加入を考えるべき人
前項までは、公的保険である程度のリスクはカバーできており、生命医療保険には加入しないという選択肢もある。というお話をしてきました。
ここで逆に、民間保険加入を積極的に考えるべき人物像を考えていきたいと思います。
- 自営業
- 小さな子供がいる
- 家族の理解が得られない
- 不安感が勝ってしまう
俗にいう、リスク許容度の低い属性を持つ人です。
自営業の方が加入する、国民健康保険では傷病手当金に該当する制度がありません。
そのため、病気やケガで働けなくなってしまうと収入が途絶えてしまいます。
病気やケガをカバーする医療保険や傷害保険、もしくは収入を保証する就業不能保険などで備えることが選択肢の一つとなりえます。
まだ小さな子供がいて、将来の見通しが立たない場合は民間保険を用いて厚めに保険を掛けておくのも良いでしょう。家族の理解が得られない場合も同様です。
共通するのは、不安感が勝ってしまっている状態ということ。
なにも、生命医療保険をゼロにしなければいけないわけではありません。
公的保険だけでは足りないな。と思う分については民間保険への加入も検討しましょう。
【注意】削ってはいけない保険
最後に、民間保険でも加入するべきものを解説していきます。
保険無くしては払いきれないリスクについては民間保険への加入を検討する必要があります。
対人の交通事故や、他人に何かしらの損害を与えてしまった時の支払いは高額になりやすく、大きな損害を与えてしまっていた場合は数千万~数億になってしまうことすらあり得ます。
更に、こういった賠償責任は自己破産しても原則免責されないため、その後の人生に大きな影響を及ぼしてしまうでしょう。
民間保険以外で備えようが無い、高額な損害リスクがあること
- 火災保険
- 自動車保険
- 個人賠償責任保険
これら保険に加入するのは、自分自身や家族のためになるのはもちろん、万が一他人に損害を与えてしまった時に、金銭的な補償で救済するためにも大切なものなのです。
保険料見直しによる節約効果
では、保険料の見直しでどの程度の効果が得られるのでしょうか?
| 保険金の平均値 (有事の際に支給されるお金) | 保険料の平均値(年/月) |
|---|---|
| 1936.1万円 | 35万2500円/約3万円 |
参考:2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」(2025年1月発行)(生命保険文化センター)
約2000万円の補償を掛けるのに、毎月約3万円を支払っていることが分かる!

実際、私も新卒時に進められるまま入ってしまった保険は月額1万円、数年で1.4万円ほどになっていました。
生命保険の加入をゼロにするのは不可能として、保険の見直しをして3万円から削っていくのは十分に可能なのではないでしょうか。
FIREを目指す以上、浮いた保険料は資産形成に回すのが重要です。
保険料を払ったと思って、投資に回しておけば自前の保険金を作ることに繋がります。
毎月そのまま、年利回り4%の積立投資に回した場合、どのくらいの節約になるのでしょうか。
| 節約額 | 5年後 | 10年後 | 20年後 | 30年後 |
|---|---|---|---|---|
| 5000円 | 330,895円 | 733,480円 | 1,819,209円 | 3,426,353円 |
| 1万円 | 661,790円 | 1,466,959円 | 3,638,417円 | 6,852,706円 |
| 1.5万円 | 992,685円 | 2,200,439円 | 5,457,626円 | 10,279,058円 |
| 2万円 | 1,323,580円 | 2,933,918円 | 7,276,835円 | 13,705,411円 |
| 2.5万円 | 1,654,476円 | 3,667,398円 | 9,096,043円 | 17,131,764円 |
| 3万円 | 1,985,371円 | 4,400,878円 | 10,915,252円 | 20,558,117円 |
なんとも恐ろしいことに、平均通りの保険を掛けていると30年で2,000万円に達してしまいます。
老後2,000万問題も解決してしまうくらい、生命保険とは大きな買い物なのです。
新卒時から30年と言えば、まだまだ現役の50代。
この間に亡くならなければ払い損になってしまうということです。
リスクヘッジは公的保険に任せて、民間保険には入らず資産形成に回したい。というのが個人的な感想です。
資産形成しておけば、何かあった時にお金として使えます。
FIREに向けて計画通りに積立投資ができるチカラがあれば、生命医療保険は必要最低限で良いと言えるでしょう。
まとめ
生命医療保険は必要なのか。
資産形成ができる習慣を持っていれば公的保険+貯蓄で十分に賄えることが多く、最低限の加入で事足りると考えられます。
結論!
民間保険には入らず、自前保険金を作るのも一つの手!
リスクヘッジは公的保険で十分なケースも多い
リスク許容度が低い場合のみ要検討
原則不要/見直し予知あり
- 独身/扶養なし
- 生活防衛資金あり
- 会社員
- 団信加入済み
加入検討/慎重にリスク管理
- 小さな子供あり
- 先進医療を希望
- 自営業/フリーランス
- 団信なしローン持ち
個人的な意見としては以下がバランスが良いと思っていますが、個々の状況やリスク許容度によっても変わってくるので参考までにしてください。
- 100万円ほど貯めるまでは医療保険のみ加入
- 保険を解約して積立投資を開始
- 子供など背負うものができたら、資産と相談しながら最低限の生命保険に加入
最後までお読みいただきありがとうございました!
↓公的保険について、もっと詳しく学びたい場合↓

FP3級の勉強をするのが最強!資格を取らなくても勉強する価値大アリ!
お金に困らない人生を送ることができるようになりますよ!